実質賃金は7か月連続マイナスに再修正
厚労省が7月の実質賃金を+0.5%から−0.2%へ修正。名目賃金+3.4%でも物価に追いつかず、家計の購買力は弱含みのまま。出典:Reuters
実質賃金とは?物価と税金を踏まえた本当の給料の見え方
「給料が上がったのに生活が楽にならない」と感じたことはありませんか?その答えのカギを握るのが「実質賃金」という指標です。ニュースでもよく耳にしますが、名目賃金や物価、税金との関係を理解すると、日々の家計感覚とのズレが見えてきます。
名目賃金と実質賃金の違い
名目賃金とは、会社から支払われる給与の「額面そのまま」の金額です。基本給や残業代、ボーナスを含む総支給額で、税金や社会保険料は差し引かれていません。一方、実質賃金はこの名目賃金を消費者物価指数(CPI)で調整したものです。つまり、物価が上がれば実質的な購買力は下がり、逆に物価が落ち着けば実質賃金は上がります。
実質賃金の計算はシンプルで、おおむね以下の式で表せます。
実質賃金の伸び率 ≒ 名目賃金の伸び率 − 物価上昇率
例えば、名目賃金が+2.5%、物価が+2.7%なら、実質賃金は▲0.2%。この場合「給料は増えたが、物価に負けて購買力は下がった」ことを意味します。
税金と社会保険料の影響
ここで注意したいのは、実質賃金は税引き前の額面ベースで算出されるという点です。私たちが実際に使えるのは税金や社会保険料を差し引いた「手取り」ですが、実質賃金にはそれが考慮されていません。つまり、名目賃金が上がると同時に税金や保険料も増えるため、手取りベースで見ると統計以上に厳しい現実に直面することが多いのです。
特に日本の所得税は累進課税制度を採用しており、収入が上がれば税率も高くなります。結果的に、額面では数%増えていても、手取りはそれほど増えず、物価上昇を差し引くと「実質的な生活水準はむしろ下がっている」という状況になりかねません。そこで….。
給料が増えても物価と税金に負けたら意味がない?若い世代こそ投資を考えよう
「今月から給料が上がった!」と聞くと、誰しも嬉しくなります。ところが、その給料の増加が物価上昇率を下回っていたらどうでしょう。実は、手取りが増えたはずなのに、生活の実感としてはむしろ苦しくなるケースがあるのです。
例えば、名目賃金(額面の給料)が2.5%増えて40万円から41万円になったとします。しかし物価が同じ時期に2.7%上がっていたら、実質的な購買力は前年より減っている計算になります。統計では「実質賃金−0.2%」と表されますが、要するに「給料は上がったのに、モノやサービスの値段の伸びに追いつけず、実際は買えるものが少なくなっている」ということです。
さらに忘れてはならないのが「税金と社会保険料」です。上に書いたとおり名目賃金や実質賃金の統計は税引き前の数字をベースにしています。しかし私たちが実際に使えるお金は、そこから所得税・住民税・社会保険料などを差し引いた「手取り」です。給料が上がると、税金や保険料も同時に増えるため、手取りの伸び率は名目賃金ほど大きくなりません。特に日本は累進課税制度なので、収入が増えるほど税率も上がり、増えた分がそのまま可処分所得に反映されにくいのです。
つまり、統計上「実質賃金が−0.2%」と出ているとき、実際の家計感覚ではそれ以上に厳しくなっている可能性があります。物価に負けて購買力が減っているうえに、税負担が重くなり、残る手取りがさらに圧縮されるからです。「給料が上がったのに生活が楽にならない」と感じる背景には、こうした二重三重の要因が潜んでいます。
ではどうすれば良いのでしょうか。その一つの答えが「投資」です。もちろん投資にはリスクがあり、短期的に値下がりすることもあります。しかし、現金や預金のままではインフレにも税金にも太刀打ちできません。銀行に預けても年0.001%しか利息がつかない一方で、物価は毎年2〜3%ずつ上昇していきます。これでは資産が目減りする一方です。
投資信託や株式、ETFなどに積立を行えば、長期的には物価上昇率を上回るリターンを得られる可能性があります。過去の世界株式市場の平均リターンは年5〜7%前後とされ、時間をかけて積み立てることで「複利」の力が働き、資産は大きく成長していきます。さらに、若い世代にはNISAやiDeCoといった税制優遇制度も用意されています。これらを活用すれば、投資によるリターンだけでなく税負担の軽減効果も得られるため、「税金に削られる」という弱点を補うことができます。
若い世代ほど、時間という最大の武器を持っています。月々数千円でも積み立てを始めれば、10年、20年後には大きな差になります。給料が増えても物価や税金に押しつぶされる前に、「お金にも働いてもらう仕組み」をつくることが重要です。名目の数字に安心するのではなく、手取りベースでの購買力を意識し、その差を埋めるために投資を味方につけること。これが、これからの時代を生き抜く若い世代に必要なマネー戦略です。

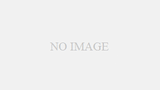
コメント